ぐっばい、アメリカ
所長 毛利 一平
1996年の夏、ボクは生まれて初めてアメリカに行きました。
奈良県立医大の衛生学教室で助手として働き始めて1年、衛生学・公衆衛生学を教える立場に立つには、勉強不足を実感していたころです。この分野で基本となる疫学の基礎を学びなおしたいと思って、アメリカの大学院で2週間のサマーコース(短期集中講座)に参加しました。
当時、日本での疫学の地位はまだまだ低く、1991年に学会(日本疫学会)が設立されたばかりで、日本語の教科書も数えるくらいしかなかったと思います。大学で専門的に教えてくれるところもなく、本格的に学ぶにはヨーロッパやアメリカに出かけていくしかありませんでした。
とりわけアメリカでは多くの大学に公衆衛生を専門的に学べる大学院(公衆衛生大学院)があり、夏休み期間ともなると疫学を集中的に学ぶことができるサマーコースがあちこちで開かれていました。1年とか2年の留学となると経済的にも大変ですが、2週間ぐらいの短期のコースならばなんとかなります。
初めてのアメリカ、パスポートと帰りの航空券を握りしめて、デトロイトの空港に降り立ちました。ビザはありません。短期間だし、観光じゃないんだけれど、別にいいでしょ。そう思いながらも、もし入国審査で引っかかったらどうしようなどと、かなりドキドキしていたのを思い出します。
入国審査では本来の審査官のほかにもう一人、研修中の(?)新人さんがいました。
(審査官)お前何しに来た(超意訳)
(ボク)あ、あの、勉強です。ミシガン大学で疫学のサマーコースに参加するんです!
(審査官)ほう、そうか
(審査官)(新人に向かって)な、夏休みともなると、世界中からこうしてアメリカに勉強に来るんだよ!
(審査官)OK! がんばれよ(超意訳)
審査官は終始笑顔だったし、この時期特有の事情を新人に向かって説明する様子は、ちょっと誇らしげだったように思います。英語もまだまだ流暢ではなかったけれど、歓迎してもらえた気がして、緊張がすっと解けました。
サマーコースは素晴らしかったです。アメリカ中、世界中から集まった学生たちとともに、教科書や最先端の論文の著者としてしか知らなかった研究者たちの講義を聞き、議論ができるわけですから! この分野でアメリカが世界中から人を引き付ける理由がよくわかりました。
思えばアメリカはボクにとって矛盾に満ちた国でした。原爆を落とす、「世界の警察」を気取ってあちこちで紛争を引き起こす。その一方で、ベトナム戦争では大規模な反戦運動があり、その後も人権や社会の多様性が脅かされる事件が起こるたびに、それらに対峙する人たちが必ず大きなうねりとなって現れる。どうしようもなく傲慢で、でもどうしようもなく素敵な国だったと思います。
それがトランプ大統領の登場でがらりと変わってしまいました。いや、ずいぶん前から幻滅することの方が多くなっていたような気はしていたのですが、トランプさんにとどめを刺されたような気がします。
イスラエルによるパレスチナへの攻撃を批判する、本当に当たり前のことなのに、それに対して「反ユダヤ」だとか「テロリスト」だとかのレッテルを貼り、権力によって自由を奪う。学生たちのデモを容認したことで大学の存在を真っ向から否定する。到底考えられないことばかりです。
ただこの問題、トランプさん個人を非難したところでどうにもならないところがこわいです。トランプ的なものが主流となってしまう、その社会こそが恐ろしいのだと思います。気が付けばイギリスからもドイツからも、似たようなニュースが毎日届きます。そして日本からも。感染症でもあるまいし、なんでこんなに世界中に広がってゆくのでしょう。
今朝(7月22日、参議院選挙が終わったばかりです)、テレビのニュースを見ていると、若い男性のこんな言葉が耳に飛び込んできました。
「外国人がのさばっているでしょ。ああゆうの嫌なんっすよ」
「のさばっている」という言葉が、耳について離れません。なぜそんな言い方をする? どうしてこんなことになった?
ぐっばい、アメリカ
あこがれていたアメリカは消えてゆくかのようですが、それでも抗おうとする人々の声が聞こえてくるのが救いです。国家だとか政府だとか、あてにはできないけれど、そうした人々とつながって希望をつなげていきたい、心からそう願っています。
P.S. 旧中川でボートを漕ぎ始めました。日曜日の朝、4人乗りでゆりのき橋から江東新橋あたりまで往復していると思います。見かけたら応援してください。

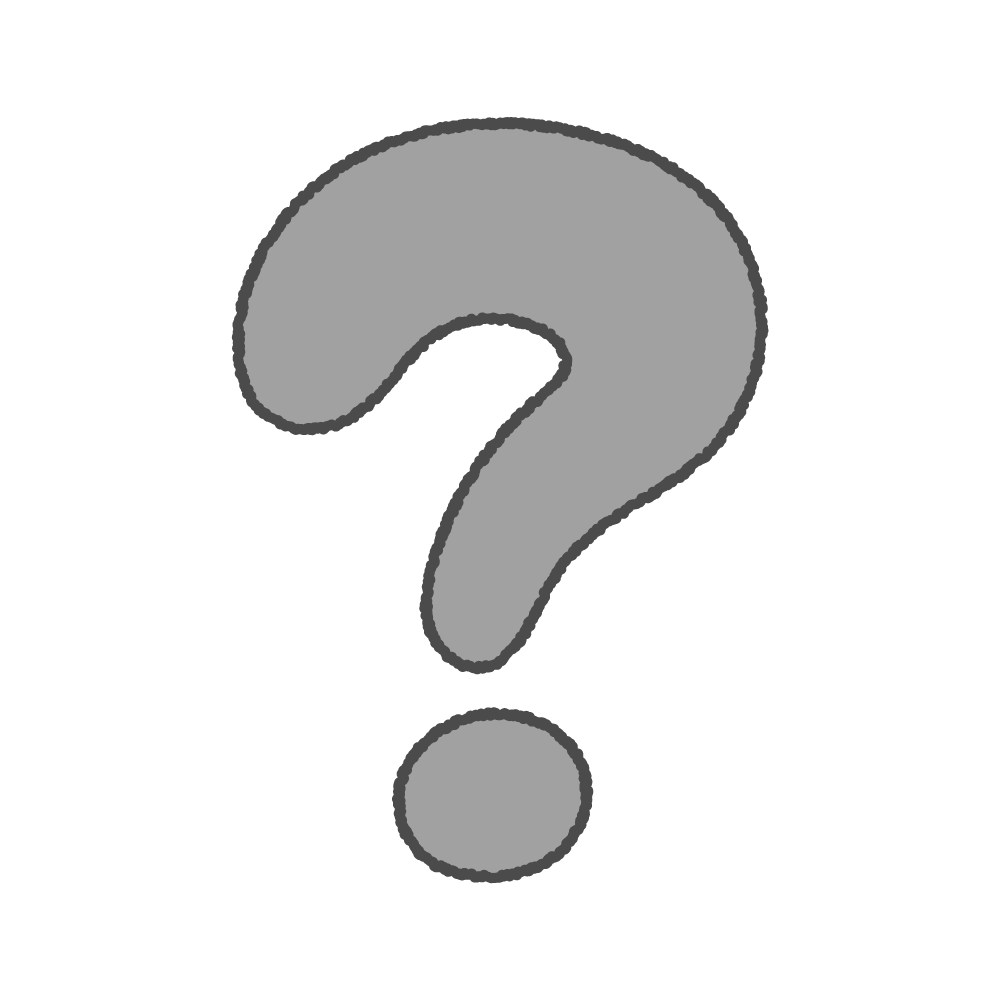
あれっ、こんな国でしたっけ・・・。
